ゴルフ場M&Aの最新トレンドと成功事例4選!これからの市場を読み解く
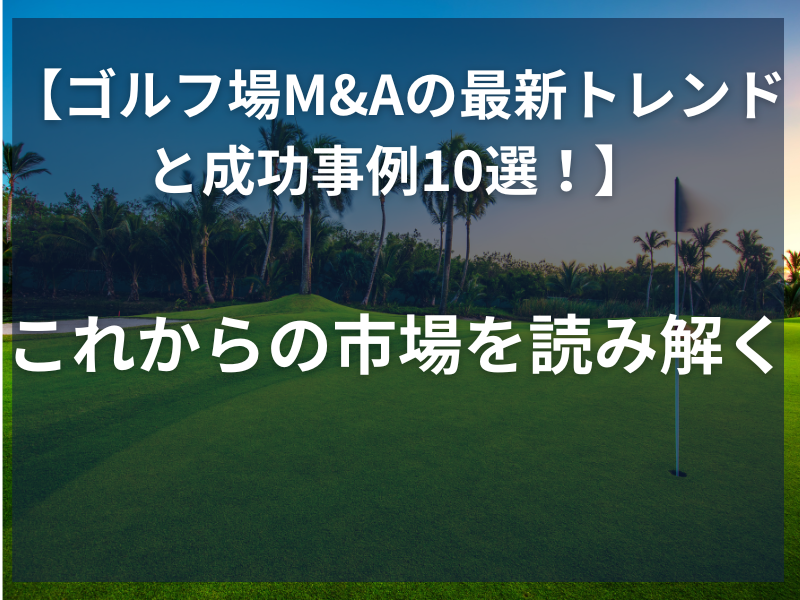
ゴルフ場M&Aの市場動向と背景
課題①:預託金返還の問題
バブル崩壊後、ゴルフ場業界の市場規模は減少し、多くのゴルフ場が廃業・倒産に追い込まれてきました。一般社団法人ゴルフ場経営者協会によると、2025年8月時点で国内のゴルフ場数は2,168(速報値)。 その多くが民事再生法などの法的整理を経験しており、経営面での課題を抱えています。過去には年間で二桁に及ぶ法的手続の申請が見受けられ、会社更生法や民事再生法を適用しつつ営業を継続している企業も存在します。
特に、預託金の返還をはじめとした債務問題は深刻です。会員が退会する際に返還請求ができる預託金の問題が経営を圧迫し、この問題を解決する手段としてM&Aを選択するケースも少なくありません。特に「2025年問題」では、ゴルファーのリタイアに伴う預託金の償還が増えることが想定されており、ゴルフ場経営者にとって多額の負債である預託金の返還は困難です。
課題②:プレー人口の減少・高齢化
日本のゴルフ人口は、1994年のピーク時の1,200万人から550万人まで減少しました。また、2024年のゴルフ(コース)参加人口は480万人で、500万人を割り込みました。
ゴルフ場の市場規模はバブル期のピーク時と比較して回復しきれておらず、市場規模の回復には1人当たりの売上高を高めるような動きを業界全体で行うことが求められています。特に若年層のゴルフ離れが進んでおり、若者層へのアプローチが必要不可欠です。
こうした経営課題を解決する手段として注目を集めているのが、M&Aです。経営の安定化だけでなく、負債処理や規模の拡大、アクセス改善といった課題に対応する一助となります。また、大手企業や投資ファンドが積極的にゴルフ場M&Aに乗り出しており、相場価格の上昇や案件の多様化が市場を活性化させています。
地域別の市場動向
ゴルフ場M&Aの動向は、地域ごとに異なる特徴を持っています。都市部に立地するゴルフ場はアクセスの良さから安定した需要がありますが、地方のゴルフ場は集客難による経営難に陥ることが多いです。一方で、地方には広大な土地や自然環境を活かして差別化を図れる可能性もあります。そのため、地域特性を加味したM&A戦略が求められるのです。
インバウンド需要
インバウンドの増加はゴルフ業界にとっても好機となっています。特にアジア圏からの観光客の需要が高まっており、海外からのゴルファーをターゲットにしたサービス強化がポイントとなっています。このような需要を見込んだM&Aは、ゴルフ場の価値向上に繋がるだけでなく、観光業界全体の相乗効果も期待できる重要な戦略です。
ゴルフ場M&Aのメリットとリスク
メリット①:運営の効率化
M&Aは事業基盤を安定させるために、収益の柱を複数作れるようにする手段として有効です。そのため、ゴルフ場の経営において、経営の安定化を図るための有力な手段となります。
特に、利用者数の減少や高齢化による収益減少が課題となる中、事業譲渡や株式譲渡によって新たな投資や運営ノウハウを取り込むことが可能です。大手企業や投資ファンドによる買収では、規模のメリットを活かした集客力や運営効率化が進められており、新たな収益基盤の構築につながっています。
メリット②:負債処理とリスク回避
ゴルフ場M&Aの目的の一つとして、負債処理が挙げられます。多くのゴルフ場は過去のバブル期に発生した預託金問題を抱えており、この債務を適切に処理することが必要不可欠です。特に、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」では、ゴルファーのリタイアに伴い預託金の償還が増えることが想定されています。
M&Aを活用することで、売却側はこれらの債務を整理しつつリスクを軽減でき、買収側も負債状況を精査した上で適切な条件のもと買収を進められます。これにより、経営者双方がリスクを回避し、売却後の安定運営が実現されます。
買収側が留意すべきポイント
ゴルフ場M&Aを成功させるためには、買収側が留意すべきポイントがいくつかあります。
債務状況をもとに適正な買収額を算出
まず、現時点の債務状況を細かく確認し、預託金や土地評価額などのデータを基に適正な買収額を算出することです。
デューデリジェンス(DD)における財務調査では、預託金の返還スケジュールや設備投資の必要性などの確認、また法的調査では土地の権利関係や各種許認可の確認も行われます。これらの情報を基に、企業価値評価(バリュエーション)を行い、適正な買収額を算定します。
収益の安定性を評価
会員の属性や利用者の満足度調査の結果、大手予約サイトからの集客状況の分析を行い、収益の安定性を評価する必要があります。
買収側にとって、ゴルフ場をM&Aするメリットの一つは会員を増やせる点です。そのため、安定して利用する会員がいることは買い手の評価を高めるポイントになります。買収側が収益の安定性を評価する際には、継続利用している会員が多いかどうか、また利用者層の構成(高齢化の度合い、若年層の取り込み状況など)を把握することが重要です。
買収後は、それぞれのブランドの良さを柔軟に発揮し、顧客満足度を上げることが鍵となります。ゴルフ場の魅力や顧客層(国や地域、所得層等)を分析し、それぞれのゴルフ場の考え方に即した誘致戦略を設定する必要があります。
事業譲渡と株式譲渡の違い
ゴルフ場M&Aにおいては、「事業譲渡」と「株式譲渡」のどちらの形で進めるかによって、手続きや影響が大きく異なります。
事業譲渡では、買収側は必要な資産や負債を選別して引き継ぐことができます。複数のゴルフ場を運営している会社が、採算の取れない部分を売却し、採算の取れる経営に集中する戦略を取る場合に適しています。
一方、株式譲渡は、手続きが簡便であるというメリットがあります。原則として、会社の法人格はそのまま存続し、事業用の機械設備、取引先、顧客、従業員などもそのまま引き継がれるケースが多いです。また、ゴルフ場事業を営むための許認可(クラブハウス併設の飲食業や浴場運営のための許認可など)も株式譲渡では引き継げるため、譲受側が新たに取得する必要がないという利点があります。
ただし、株式譲渡の場合は、全株主の同意が必要な点に注意が必要です。また、会社そのものを売却するため、中小のゴルフ場会社が経営再建や事業拡大のために大手の傘下に入りたい場合に適していますが、会員権を持つ既存会員への影響についても考慮が必要です。
ゴルフ場M&Aの成功事例4選
成功事例1:アコーディア・ゴルフによる買収
アコーディア・ゴルフは、PGMホールディングスと並んで国内ゴルフ場における市場のリーディングカンパニーの一つです。ゴルフ場保有数・運営数で国内最大手のゴルフ場運営会社グループです(2024年11月末時点で173カ所)。アコーディアは、外資系ファンドの傘下で巨額の資金を利用し、経営状況が悪化したゴルフ場を買収し、再生させてきました。
2018年には、麻生カントリークラブ、富士の杜ゴルフクラブ、宇津峰カントリークラブといったゴルフ場をアコーディア・ゴルフが取得しています。また、2022年9月には鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部松元コースを買収しています。全国展開しているアコーディアのノウハウを活かして成長していくことが期待されています。
成功事例2:地方ゴルフ場の経営改善
地方のゴルフ場においては、プレー人口の減少や設備の老朽化が課題として挙げられます。しかし、ある地方ゴルフ場ではM&Aを通じて経営再建を果たしました。この事例では、買収後に地域コミュニティとの連携を強化し、地元企業とのタイアップによる法人会員の獲得に成功しました。また、地域イベントを定期的に開催することで新たな顧客層を取り込み、老舗ゴルフ場としての魅力を再発見させたことが再生の大きな要因となりました。
ゴルフ場運営大手の太平洋クラブは、2021年に金乃台カントリークラブ(茨城県)の経営権を取得しました。金乃台カントリークラブは、日鉄日新ビジネスサービス株式会社の子会社である株式会社金乃台が運営していました。しかし、プレー人口の減少により運営が厳しくなっていました。安定的な運営ができる事業者を探していたところ、太平洋クラブとのM&Aが実現しました。
成功事例3:インバウンド対応での価値向上
近年のインバウンド需要の増加は、ゴルフ場M&Aに新たなチャンスをもたらしています。2015年には、中国系の上海豫園(復星グループ系)が、スキー場・ホテル・ゴルフ場を含む総合リゾート「星野リゾート トマム」の所有株式を取得しました。
トマムは外国人(特に中国を含むアジア圏)に人気があり、買収時からインバウンド需要の取り込みが期待されていた資産です。運営は星野リゾート側が継続して行い、多言語情報やインバウンド向けパッケージを整備する動きが見られます。
成功事例4:廃業危機からの復活
「信州伊那国際ゴルフクラブ」(36ホール)の旧経営会社、株式会社信州伊那國際ゴルフクラブ(東京都千代田区)は、2024年1月24日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令および監督命令を受けました。この法的整理の背景には、市況の低迷やゴルフ人口の減少による利用客の伸び悩み、そして預託金の償還問題による資金繰りの悪化がありました。負債総額は会員約3,000名からの預託金を中心として、約33億円に上りました。
同社は事業を継続するため、まずは債務を除いたゴルフ場事業を、2024年1月に吸収分割手続により新会社である伊那国際ゴルフクラブ株式会社(子会社)へ移管しました。
その後、裁判所の許可を得て、入札で選定されたスポンサー企業である坪井工業株式会社(東京都中央区、一般土木建築工事)に対し、新会社(伊那国際ゴルフクラブ株式会社)の全株式1株を2024年3月1日付けで譲渡しました。譲渡代金などは債権者への配当の一部に充当される計画であり、会員のプレー権は保護される方針が示されました。
これからのゴルフ場M&A市場の展望
若年層や女性ゴルファーに向けた戦略
従来、ゴルフは中高年層をメインターゲットとしていましたが、ライフスタイルの多様化や健康志向の高まりにより、若年層や女性の関心が急速に高まっています。この流れを受けて、買収後のゴルフ場では、女性専用のラウンジやベビールームの整備、若い世代が楽しめるモダンなカフェの併設など、施設のアップデートが求められています。また、SNSを活用したプロモーションや、初心者向けのスクール運営による集客強化も効果的です。
アフターコロナ時代のM&A市場予測
リモートワークの普及や海外旅行の制約が影響し、国内での余暇活動が見直される中、ゴルフは密を避けて楽しめる娯楽として再評価されています。この流れにより、ゴルフ場の利用者数は回復傾向にあり、M&A案件への関心も増加しています。また、コロナ禍における経営不振で売却を検討する施設も増加しており、市場全体で中小規模の案件が増える見込みです。ただし、買収後の設備投資計画や経営改善策を織り込んだ慎重な戦略が重要となります。
AIとデータ活用が生む新たな可能性
M&Aによるゴルフ場取得後、独自の運営データや地域特性を反映したマーケティング施策をAIで最適化することで、利用者数の増加や売上アップが期待されます。例えば、予約データを分析して混雑予測を行い、適切な価格変動を設定する動的プライシングの活用や、利用者属性に応じたターゲティングキャンペーンの実施が考えられます。また、スマホアプリを通じたコース案内やポイント管理など、デジタル化を進めることで顧客満足度も向上します。
環境問題への対応
環境問題が大きな話題となる中、ゴルフ場の運営においてもエコロジーへの配慮が求められています。M&Aによる買収後、環境負荷を軽減する施策を展開することで、新たな価値創出につながります。具体的には、農薬や化学肥料の使用を減らしたコース管理、水資源の効率的な利用、再生可能エネルギーの導入などが挙げられます。また、環境に優しい施策を実施することで、CSR(企業の社会的責任)の一環としてアピールが可能となり、利用者や地元住民からの支持を得ることができます。
今後注目されるエリアとターゲット
ゴルフ場のM&A市場では、地域ごとの特性やターゲット層に注目した戦略が重要です。都市近郊のエリアは引き続き高い需要が見込まれますが、近年では地方エリアやリゾート地におけるゴルフ場のポテンシャルにも注目が集まっています。特に観光地や交通網が整備されつつある地域では、インバウンド需要の再開を見据えた施設改修やマーケティングが期待されます。また、高齢者層に加えて若年層やゴルフ未経験者向けのコンテンツを強化することで、新たな顧客基盤の構築が可能です。こうしたエリア別の特性を考慮した買収計画が、M&A成功の鍵となります。
記事の新規作成・修正依頼はこちらよりお願いします。










