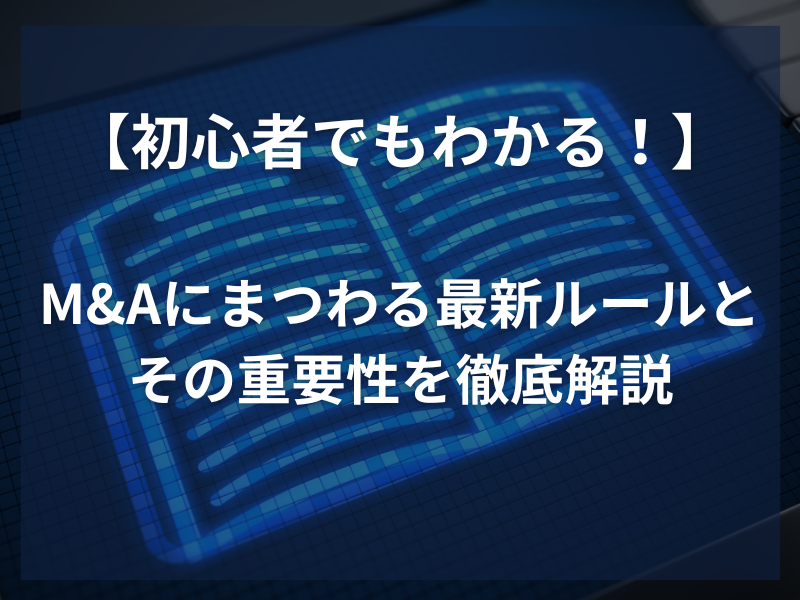2025年日本企業のM&A件数が過去最多に!その背景と未来の展望を探る

2025年の振り返りと2026年現在のM&A概況
M&A件数の推移と記録更新までの背景
2026年現在、日本国内のM&A活動は極めて高い水準を維持しています。2024年のM&A件数は4,449件(レコフデータ調べ)を数え、続く2025年も適時開示ベースで5年連続の過去最多を更新しました。この活況の背景には、構造的な「事業承継問題」があります。2025年という節目を経た今もなお、多くの中小企業経営者が引退時期に直面しており、後継者不在による黒字廃業を防ぐための「第三者承継型M&A」が定着しています。中小企業庁の試算によれば、依然として約127万人の経営者が後継者未定の状態にあり、この課題解決が市場の主要な牽引役となっています。
また、国内企業間の取引(IN-IN)は2025年に向けてさらに加速し、取引総額は20兆3,870億円と過去最高を記録しました。これはトヨタグループによるグループ再編などの超大型案件が寄与した結果です。一方で、日本企業による海外買収(IN-OUT)も2025年には回復基調を見せ、円安環境下にあっても成長戦略を優先する「選択と集中」の姿勢が鮮明になっています。こうした傾向は、日本企業の経営戦略においてM&Aが不可欠な手法として確立されたことを示唆しています。
主要産業別のM&A件数の傾向
業界別では、依然として製造業、小売業、サービス業における事業承継を目的とした案件が多数を占めています。これらのセクターでは、労働力不足やコスト高騰といった外部環境の悪化に対し、M&Aを通じた規模の経済の追求や効率化を図る動きが加速しています。一方、IT・デジタル領域では、非連続的な成長を実現するためのスタートアップ買収が常態化しており、先端技術や専門人材の確保を狙った戦略的投資が活発です。
地方経済においても、北海道や九州を中心に、地域の基幹産業である農林水産業や建設業の再編が進展しています。農林水産業では、スマート農業の導入や輸出競争力の強化を目的とした統合が見られ、建設業では社会インフラの老朽化対応やDX推進に向けた企業間連携が深化しています。地域経済の担い手を守るという観点から、地方銀行や自治体の支援体制が整備されたことも、こうした地域特化型の取引を後押ししています。
グローバルM&A市場との比較
日本市場が拡大基調にある一方で、2025年までのグローバルM&A市場は金利上昇や景気後退懸念から、件数ベースでは調整局面を経験しました。全世界の取引件数は低迷したものの、米国を中心とした大型のディール(メガディール)は2025年後半から回復の兆しを見せています。世界的なインフレと金融引き締めにより、投資家がより厳選した案件に資金を集中させる傾向が強まっているためです。
このような世界情勢下において、日本のM&A市場は独自の成長を遂げています。クロスボーダー案件も2025年には回復を見せ、特に北米や東南アジアでの案件増加が顕著です。日本企業の豊富な手元資金と、国内市場の成熟に対応するための海外進出意欲が、グローバルな停滞感とは対照的な動きを生み出しています。日本の市場は、地域密着型の承継問題とグローバルな成長戦略が併存する、極めて特異で活力のあるフェーズにあります。
日本国内の地域別M&A動向
地域別の動向では、東京を含む首都圏が案件数・金額ともに圧倒的なシェアを占めています。首都圏ではIT、サービス、ヘルスケア分野を中心とした「事業ポートフォリオの再構築」を目的とする戦略的M&Aが主軸です。一方で地方都市においては、北海道や九州、東海地域などで「地域経済の維持」に主眼を置いた事業承継型案件が質・量ともに向上しています。
特に北海道では、一次産業のDX化や、観光インフラの再編を目指したM&Aが注目を集めています。ポストコロナにおけるインバウンド需要の本格回復に伴い、ホテル・旅館の経営統合や、サービス水準の向上を狙った広域的な資本提携が進行しています。こうした地域ごとの課題に即したM&Aの展開は、単なる企業の売買を超え、地方創生の実効的な手段として機能し始めています。
日本企業によるM&A増加の背景
事業承継問題の深刻化と承継支援の拡充
M&A件数が高止まりしている最大の要因は、中小企業の経営陣が直面している「出口戦略」としての需要です。2025年を過ぎた今、経営者の引退ラッシュはピークを迎えており、黒字であっても後継者が確保できない企業にとって、M&Aは雇用と技術を守るための唯一の選択肢となりつつあります。政府もこれを重要視し、事業承継税制の適用期限延長や、M&A支援機関の登録制度による透明性向上など、環境整備を徹底しています。
また、承継型M&Aは「親族外承継」の有力な手段として広く受容されるようになりました。かつてのM&Aに対する「乗っ取り」という負のイメージは払拭され、地域経済や取引先との関係性を維持しつつ、新たな資本のもとで第二の創業を目指す「前向きな決断」として評価されています。これが、潜在的な売り手の掘り起こしにつながり、市場の裾野を広げています。
成長を目指した戦略的M&Aの浸透
昨今のM&Aは、消極的な問題解決だけでなく、積極的に競争優位性を構築するための「戦略的ツール」として機能しています。国内市場の人口減少が確実視される中、企業が持続的な成長を遂げるためには、技術獲得、シェア拡大、そして異業種への進出を迅速に行う必要があります。これらをゼロから構築する時間的コストを回避するため、M&Aが選好されています。
2025年に記録された大型案件の多くは、デジタルトランスフォーメーション(DX)やサステナビリティ(GX)への対応を目的としたものでした。特にカーボンニュートラル実現に向けたエネルギー関連の再編や、AI技術を自社事業に統合するためのIT企業買収などは、企業の生存戦略に直結する動きとして増加傾向にあります。
TOBおよび非公開化の加速とその影響
株式公開買付け(TOB)の活用も、かつてない活況を呈しています。2025年のTOB件数は過去最多を更新しており、その背景には東証による「資本コストや株価を意識した経営」の要請があります。親子上場の解消やMBO(経営陣による買収)を通じた非公開化を選択する企業が増えており、意思決定の迅速化と上場維持コストの削減を目指す動きが顕著です。
こうしたTOBの増加は、株式市場全体の透明性とガバナンスの向上を促す一方で、アクティビスト(物言う株主)による提案への対抗策としても用いられています。日本企業が資本効率を重視する経営へと転換し、その手段としてTOBを自在に使いこなすフェーズに入ったことは、日本の資本市場が成熟した証左と言えるでしょう。
金融環境の変化と専門人材の成熟
M&Aを支える金融インフラも大きく変化しています。国内の金利環境には変動が見られるものの、M&Aファイナンスへの金融機関の意欲は依然として旺盛です。地方銀行や信用金庫がアドバイザリー業務を強化し、地域の中小企業に対してきめ細やかなマッチングを提供していることが、成約件数の下支えとなっています。
さらに、投資ファンドの存在感も無視できません。PEファンドは単なる資金提供者ではなく、買収後の経営支援(ハンズオン)を通じて企業価値を高めるプロフェッショナルとして定着しました。M&A専門の仲介業者やプラットフォームの普及も相まって、取引の効率性と安全性が向上したことが、過去最多を更新し続ける市場の土台となっています。
2025年から2026年にかけての主要なM&A成功事例
中小企業を対象とした事業承継事例
2025年には、中小企業の事業承継が成約件数の約8割を占めるまでになりました。成功事例として注目されるのは、単なる存続ではなく「シナジーによる再成長」を実現したケースです。例えば、高度な技術を持つ地方の精密部品メーカーが、大手商社の傘下に入ることで、それまで手付かずだった海外販路を一気に拡大した事例があります。これにより、雇用の維持だけでなく、従業員の待遇改善や技術の高度化が達成されており、理想的な事業承継のモデルケースとなっています。
日本企業による戦略的クロスボーダー案件
IN-OUT(日本企業による海外企業買収)では、規模の拡大だけでなく、技術的優位性の確保を狙った「質の高い買収」が増えています。2025年には、国内大手ヘルスケア企業が欧州のバイオスタートアップを買収し、次世代創薬プラットフォームを内製化した事例が話題となりました。円安によるコスト増を乗り越え、グローバルでの競争力を長期的に確保するための「攻めの投資」が、大手企業の間で標準的な戦略となっています。
スタートアップと大企業の協業・統合型M&A
オープンイノベーションを加速させるためのM&Aも活発です。特にAI、ロボティクス、フィンテック分野では、大企業が自社のリソースとスタートアップの機動力を融合させる事例が相次いでいます。大手金融機関が決済システムを持つスタートアップを完全子会社化し、従来のレガシーシステムを一新した案件は、DX推進の成功例として高く評価されました。このように、M&Aは企業のデジタル変革を最短距離で実現するための「時間購入」としての性格を強めています。
業界再編を象徴するメガディール
2025年は、業界の勢力図を塗り替えるような大型再編が相次ぎました。エネルギー業界における脱炭素シフトを目的とした統合や、物流業界での2024年問題(物流危機)に対応するための共同持株会社設立などがその代表です。これらの事例は、個社での対応が困難な社会的課題に対し、M&Aという手法を用いて業界全体の最適化を図る動きであり、2026年以降もこの流れは継続すると予測されます。
2026年以降のM&A市場の展望
事業承継支援の高度化とPMIの重視
2026年以降のM&A市場では、件数の増加とともに「成約後の統合プロセス(PMI)」の重要性が一層高まっています。これまではマッチングと成約に焦点が当たりがちでしたが、今後は買収後のシナジーをいかに具現化するかが、経営陣の腕の見せ所となります。特に中小企業のM&Aにおいては、異なる企業文化の融合や、デジタルツールの導入による生産性向上が成否を分ける鍵となります。PMIに特化したコンサルティング需要も拡大しており、M&Aの「質の向上」が求められる時代へと移行しています。
クロスボーダーM&Aの戦略的転換
世界経済の不透明感が続く中、日本企業のクロスボーダーM&Aは「地政学リスクへの対応」を組み込んだものへと進化します。サプライチェーンの分散や、友好国内での市場確保(フレンド・ショアリング)を目的とした買収が加速する見込みです。また、アジアの新興市場においては、現地の生活習慣やデジタル環境に精通したローカル企業との資本提携を通じ、単なる輸出ではなく、地域経済に深く入り込む形での成長戦略が主流になると考えられます。
業界再編の深化とESG投資の影響
今後、M&Aの判断基準としてESG(環境・社会・ガバナンス)の観点が不可欠となります。非効率な事業部門の切り出し(カーブアウト)や、環境負荷の低い事業への転換を目的としたM&Aがさらに増加するでしょう。特に製造業や化学産業においては、クリーンテクノロジーを持つ企業との統合が、投資家からの評価を維持するための必須条件となりつつあります。業界再編は、単なるシェア争いから「持続可能な社会への適応」を競うステージへと突入しています。
AIとデータサイエンスによるプロセスの再定義
M&Aの実務プロセスにおいても、デジタル技術の浸透が進んでいます。AIを用いたターゲット選定、アルゴリズムによる企業価値評価、ビッグデータを活用した潜在的リスクの早期発見(プレDD)などが普及し、取引のスピードと精度が飛躍的に向上しています。2026年以降、これらのデジタルツールを使いこなすことが、アドバイザーのみならず、企業のM&A担当者にとっても必須のスキルとなるでしょう。技術革新は、M&A市場をより透明でアクセスの容易なものへと変貌させています。
記事の新規作成・修正依頼はこちらよりお願いします。